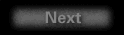|
| 金沢蓄音機館 |
東京/上野にある国立科学博物館よりも資料が豊富な金沢蓄音機館。
全国から寄贈が多く、当時の音色も実演/実聴できるから楽しいです。
カビの生えたレコードにはカビキラーが一番良いとか。
<蓄音機の歴史>
1877年に、エジソンがスタンダート・フォノグラフ(錫箔円筒式蓄音機)を開発した。
ラッパの先に針がついていて、歌ったりすると振動した針が円筒形の蝋管に刻まれ、
錫(スズ)やワックスが塗られた蝋管に録音される仕組みです。
(最初に録音されたのは「メリーさんの羊」)
↓
1887年に、エミール・ベルリナーが円盤式蓄音機「グラモフォン」を開発した。
現在のレコードプレーヤーと同じように円盤を回転させて音を再生する仕組みです。
円盤の方がコピーが作りやすく、エジソンのものよりも売れた。
↓
1925年頃に、電気式蓄音機(電蓄)が開発された。
ターンテーブルをゼンマイではなくモーターで回し、針の動きを電気信号に変換し、真空管式のアンプで増幅、
その信号でスピーカーを鳴らす仕組みです。
<記憶媒体の歴史>
錫(スズ)やワックスが塗られた蝋管
↓
SP盤(スタンダートプレイ)は大きさ25cm、78回転で約3分 録音出来る
↓
LP盤(ロングプレイ)は大きさ30cm、33回転で約25分間 録音出来る
↓
EP盤(エクステンデットプレイ)は大きさ18cm、33回転で約8分間 録音出来る
↓
磁気テープ
↓
CD
↓
DVD
↓
MPプレイヤー

|

(錫箔円筒式蓄音機) |

(蓄音機のラッパが箱の中に納まった) |

(針がダイオモンドで出来ていて音色はイイが高価) |

|

|

(当時は家が建つくらいの高価なもの) |

|
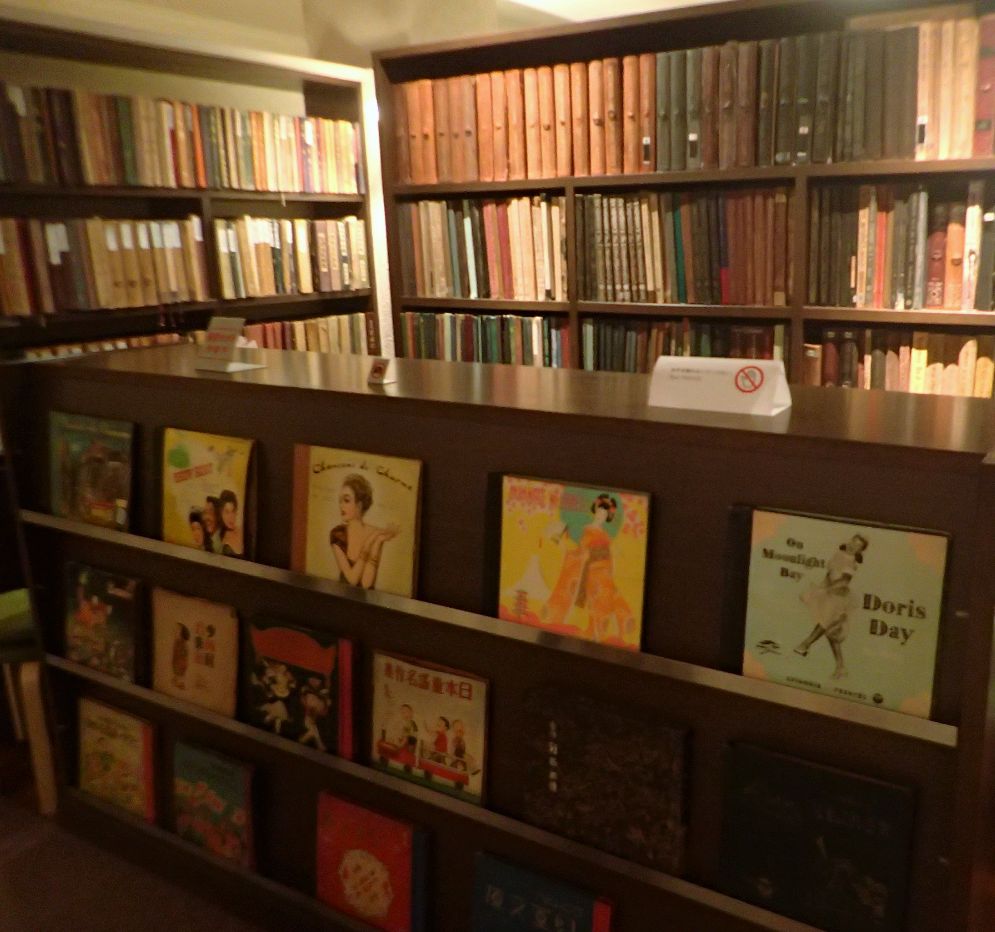
|

|

|

(酒場でよく演奏された機械) |
「大人の科学」から発売している「新エジソン式コップ蓄音機」。
簡単なプラモデル感覚で実際に組み立てて、再生&録音を試すことで
蓄音機の構造を理解出来ました。
<録音の仕組み>
ホーンに声が入ると、声で細かい振動が起き、振動が針に伝わり、コップに音の溝を波で刻む。
<再生の仕組み>
コップの溝の波が針を振動させ、振動がホーンに伝わり、ホーンから音が出る
<溝と音との関係>
・溝の波の間隔が狭い → 音が高い
・溝の波の間隔が広い → 音が低い
・溝の波の幅が大きい → 音が強い
・溝の波の幅が小さい → 音が弱い
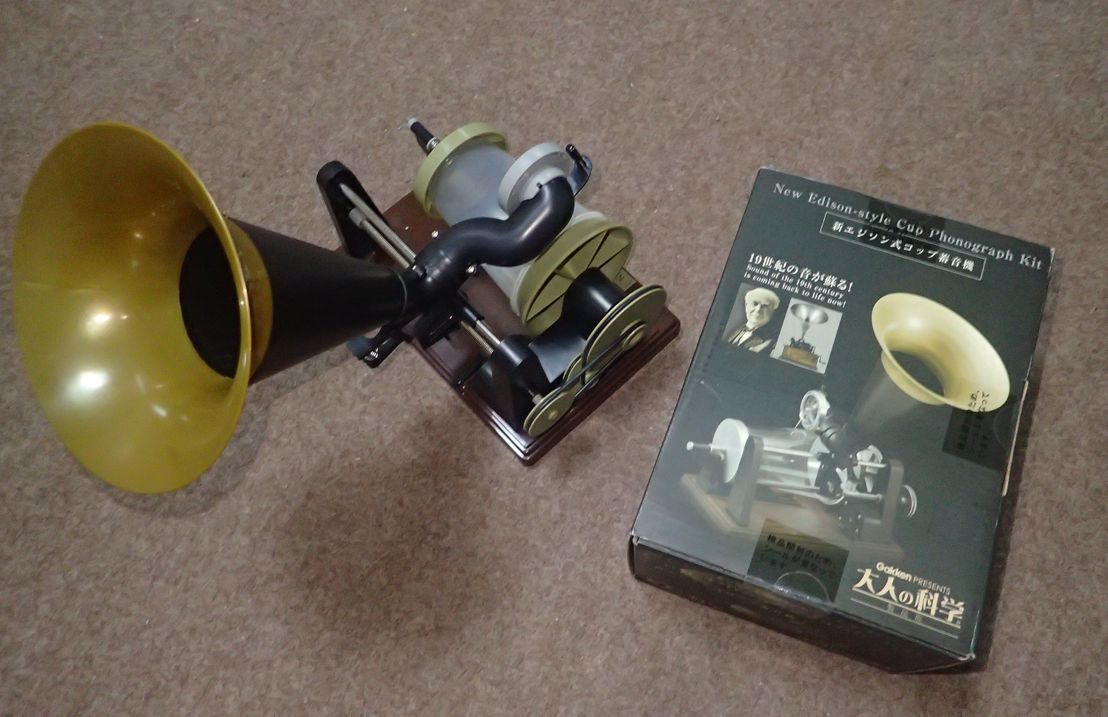
|

|

|
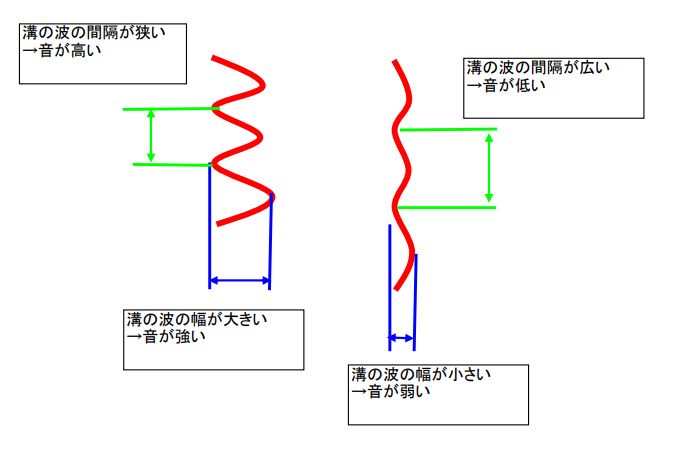
|