|
富山の薬

江戸中期 富山二代目藩主/前田正甫公が薬草研究に力を入れ、「反魂丹」という薬を製作。
お金のない農家でも利用し易いように、薬を使用した分だけお金を頂く
先用後利という手法/いわゆる置き薬で全国に広めていった。
売薬さんは半年もしくは1年に1度、置き薬を設置した家を巡り、
お金の徴収と薬の補充で各地方へと出向いて行った。
明治になり西洋医学が入ってきてからは、国内の伝統薬は衰退し始めたが、
主軸産業が薬であったこともあり富山の「反魂丹」はその危機を乗り越えて今に至った。
それら資料は以下お店や施設にも展示されているので参考までに。
・池田屋安兵衛商店
・広貫堂
・薬種商の館 金岡邸
・富山市民族民営村
・富山城
・豊栄稲荷神社

創業昭和11年の池田屋
|

丸薬製造を体験
|

昔ながらの絵柄の薬
|

当時の営業風景
|

2階のレストランで健康膳を食す
|

熊膽圓や六神丸で有名な広貫堂
|

売薬さんの当時の道具
|

広貫堂のレストランで薬膳カレーを食す
|

薬膳食材は勉強になりますね
|

薬種商の館 金岡邸
|

生薬の種類 多いデス
|

富山藩第2代藩主・前田正甫
|

駅前の売薬さんの像
|

<薬草について分かったこと>
・薬膳師とは一人一人にあった食べ物を選定する。
(血圧が低い人が高くするための高麗人参を使用した料理を、血圧の高い人が食べると危険なため、それを防止する)
・薬草や薬用植物は薬となる草でミネラルを補給して治癒力を高める効果/薬効があるが、たくさん食べても効果は変わらない(医薬品は病気を治すが)
ミネラル不足では漢方薬は効き難い。
↓
薬草を食べればいいが、薬効ある苦味は正直美味しくないのであまり食べない。
↓
代わりにサプリを取ればよいが、間の体はマグネシウムに拒否反応するため、実際95%は外に排出されてしまう。
↓
仮に1万円の薬が500円の効果しかないことになる。
↓
医者の薬は即効性はあるが、病気になり難い丈夫な体にする薬はない。
↓
スーパーの野菜は科学肥料で育っているため、ミネラルが少ない薬効も期待できない。
・薬効は苦味、渋味、えぐ味(臭い、不味い、苦い)が強いため、美味しく食べるのは難しいため、広まり難い。
(学者は薬草の効果を調べるが、美味しく食べるところまでは無関心)
・水や油に溶け易いので、フライパンで焼くなどすると、薬効が落ちる。
(30秒ぐらいならOK)(天ぷらは薬効が半分ほど抜けている)
・日本料理で水に30分以上浸けるのは、ミネラルが抜けてしまうので薬効が期待できない。。
・薬草は山と山の間の谷である沢などのミネラルが集まる場所で育ちやすい。。
・広葉樹は根を広くはるため、山の保水力が高いのでミネラルがたまり易い。。
(根が大きい→養分が葉まで行き渡る→葉が大きく育つ→落葉が腐って土の栄養になる→ミネラルが豊富な土になる)。
・針葉樹は根が少なく薬草が育ち難く、山崩れが起きやすい。
・ワラビ ゼンマイなどシダ植物は薬効が少ない 。

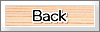
|